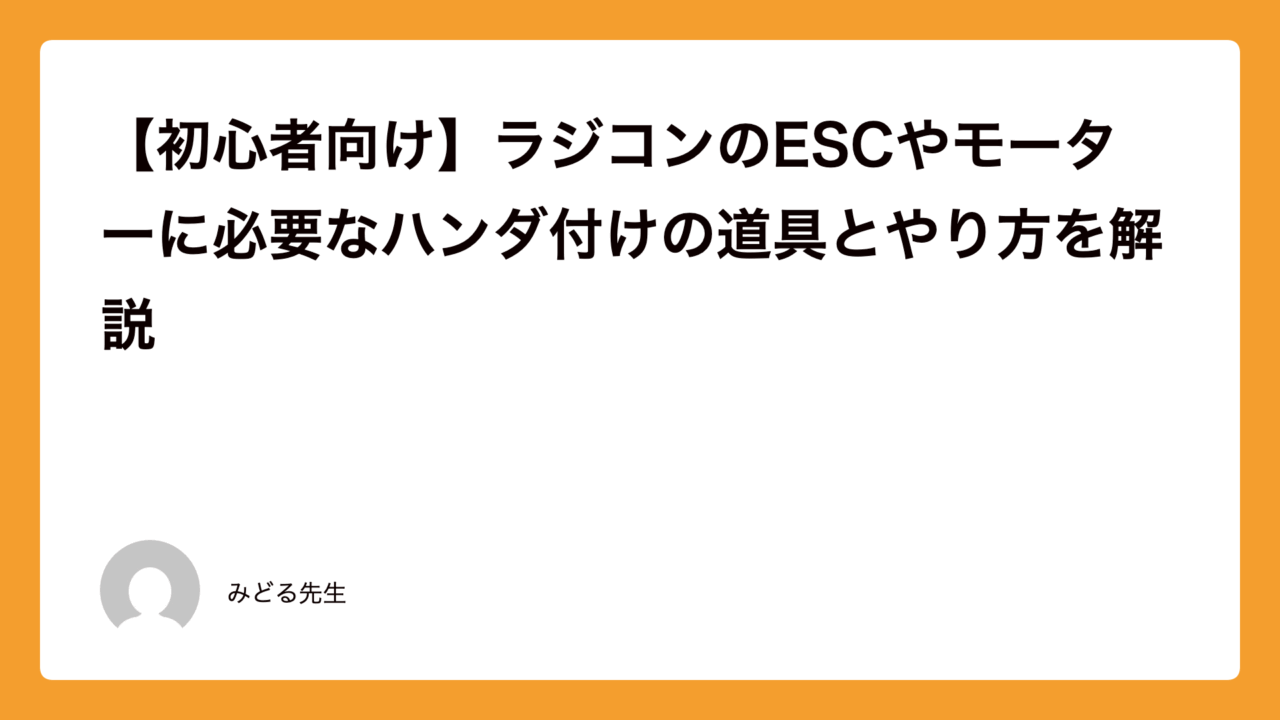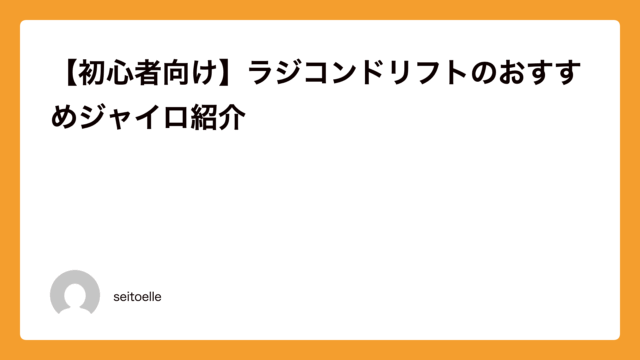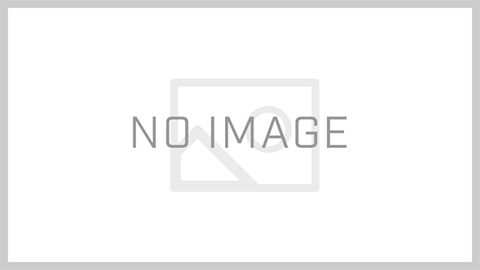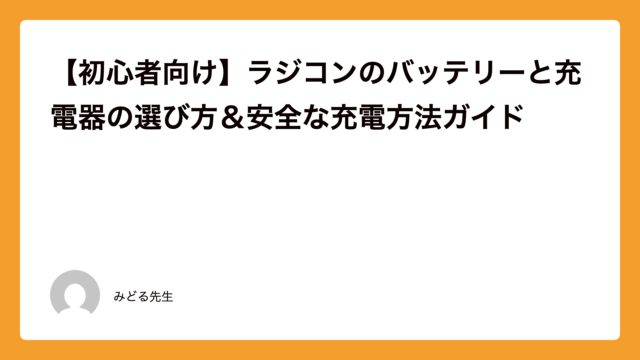ラジコン(RCカー)を始めたばかりの方にとって、
ESCやモーターのハンダ付けは「難しそう」と感じるかもしれません。
しかし、基本を押さえれば、しっかり確実に仕上げることができます。
この記事では、初心者の方に向けてハンダ付けに必要な道具や手順、注意点などをわかりやすく解説します。
なぜハンダつけが必要なのか?
ラジコンのESCや、モーターにはABCコードとバッテリーコードが購入時でハンダつけされていない製品が一部販売しています。
ミドルクラス以上の商品ではほとんどの製品にコードが配線されていない状態なので、ハンダ作業を自分で行う必要があります。
基本的な見分け方ですが、ESCであれば2万円台、モーターでは1.5万円台の製品からこういった配線されていない製品となります。
なぜ配線されていない状態で販売しているのか?

すぐ使えるように、配線して販売した方が便利だし良いんじゃないの?
たしかに、初心者でも使用できますしすぐ使用できるので配線済みで販売した方が良さそうですよね。
中級者以上のユーザーになってくると、それぞれのマシンによって配線状況が異なるので、配線済みで販売していても再度配線しなおす手間が発生してしまうのです。
それなら、配線やプラグの部材台を製品価格に加えていない状態で販売した方がメーカー・ユーザーどちらにとってもメリットがあるので配線していない状態で販売されています。
例えば、最近のラジドリだとESCをリヤにのせるか、シャーシの中央に載せるかに2分されています。
リヤに載せる場合は配線の長さが必要ですが、中央に載せる場合は配線は短くて済みます。
こういった配線状況の違いのために、コードが付属していない状態で販売されているのです。
ハンダ付けに必要な道具
まずは、ハンダ付けに必要な基本の道具を揃えましょう。
高価な道具を揃える必要はありません。
しかし、最低限の性能と必要な部材は準備しておきたいところです。
おすすめはセット販売しているハンダセット

Manelord はんだごてセット 温度調節可(200~450℃)ハンダゴテ
おすすめは上記のような一式揃ったセット販売品を購入することです。
こちらは全部揃って2500円程度なのでお手頃価格でコスパも良いです。
フラックス(ペースト)

こちらはフラックスというハンダのノリをよくし、導通を安定させる糊のようなものです。
人のものをハンダしたりしない限り、50gあればずっと使えます。
最初に買っておきましょう
第三の手
通称:第三の手とも呼ばれるハンダするモノを固定する道具は付属していません。
百均などで、クランプや大きな洗濯バサミなどを購入して、
対象物が転がったり、動いたりしないように工夫しましょう。
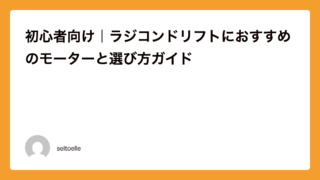
ハンダつけするために必要なラジコンの部材
ここからはハンダつけするために必要なラジコンの部材を紹介します。
L型プラグコネクタ

バッテリー 端子 4mm ヨーロピアン L型 プラグ コネクター
こちらはバッテリー用の配線に接続するためのL型プラグです。
プラスとマイナスを逆接続しないように赤と黒で色分けされており視認性が良いです。
こちらのバッテリー端子に関しては、赤と黒だけでなくさまざまな色が発売されています。
ラジコン上級者になるとこういったプラグの色味や材質にもこだわってオリジナリティを高めていますので、自分の好きな色を探すのも楽しいですよ。
ヨコモ ブラシレスモーター用コネクタセット

ヨコモ バナナ オス/メスコネクター セット ブラシレスモーター用
こちらはドリフトラジコンメーカーのヨコモから発売されているブラシレスモーター用のコネクタです。
ABCコードに配線するオスの端子と、ブラシレスモーターにハンダつけする六角メスコネクタです。
六角メスコネクタがブラシレスモーターの接続に主流の接続方法となっていて、
穴のどちら側からでもコードを接続することができるので、自由度が高いのが特徴です。
配線用シリコンケーブル

こちらはラジコンを配線する際に必要なコードです。
ハンダつけが必要なESCを購入した場合、製品に含まれていることがありますので事前に確認しましょう。
一方で、長さを間違えたり、配線に失敗してしまったり、再度配線する際に予備となる長さ分は含まれていませんので、配線用コードは事前に準備しておくことをおすすめします。
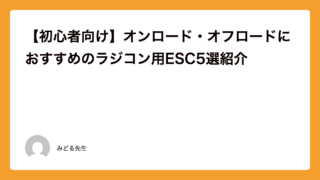
ハンダ付け前の準備
① コードの皮むき
ESCやモーターから出ているコードの被覆(シリコンケーブル)を、ワイヤーストリッパーで約3〜5mmほど剥きます。中の導線が切れないように注意してください。
② コネクタや端子の仮固定
「第三の手」やミニバイスでコネクタやパーツをしっかり固定しておくことで、安定した作業ができます。
③ ハンダゴテの加熱
ハンダゴテは十分に温めてから使いましょう(200〜350℃が目安)。
温まっていないとハンダがうまく溶けません。
ハンダ付けの手順
ステップ1:予備ハンダ(下ごしらえ)
・導線と接続するコネクタ両方に「予備ハンダ」をしておきます。
・ハンダゴテを軽く当てて、導線の芯線にハンダを染み込ませてください。
・コネクタにもフラックスを塗り、表面にハンダを少し盛っておきます。
ステップ2:ハンダで接続
・導線とコネクタを密着させた状態で、ハンダゴテを同時に当てます。
・ハンダが自然に流れて導線とコネクタの間に入り込めばOK。
・ハンダゴテを当てすぎるとコネクタが変形することがあるので、3〜5秒以内が目安です。
ステップ3:冷却と確認
・ハンダが自然に冷えて固まるのを待ちます(送風で冷ますのはNG)。
・見た目がつややかで、ドーム状になっていれば良好なハンダです。
・必要に応じてヒートシュリンクをかぶせて、ライターなどで炙って絶縁します。
ハンダつけのよくある失敗例:ハンダが玉になるだけでくっつかない
ここからはハンダつけのよくある失敗例:ハンダが玉になるだけでくっつかない現象についての原因についてです。
温度が足りない
ほとんどの場合、玉になってくっつかないのは温度不足が原因だと思います。
ハンダは高熱で素早く処理する必要があります。温度域を少し変えて作業してみましょう。
フラックス不足
フラックスが不足している場合もハンダがつきにくいことがあります。
フラックスの塗布量を調整してみてください。
ラジコンハンダつけ参考動画
こちらの動画がハンダつけについて非常にわかりやすいので参考にしてみてください
まとめ:怖がらずに練習あるのみ!
最初は緊張するハンダ付けですが、やればやるほど上達します。
最初は安いワイヤーや使わないパーツで練習し、少しずつ感覚をつかんでいきましょう。
安全のため換気もお忘れなく。

先生もハンダの経験が無かったんだけど、今では自分でハンダつけしているよ。
最初の頃は、何回も付け直したり、サーキットでハンダ部分がとれちゃったり大変な目にあったけど、回数を重ねるごとにうまくできるようになったからみんなも挑戦してみよう

✅ 当サイトから最も売れているラジドリシャーシ・メカ類はコチラ!
販売数量から厳選した初心者〜中級者用おすすめモデルです。
迷ったらまずはこの組み合わせをチェックしてください!
【シャーシ】
▶ ヨコモ RD2.0
→ 初心者向けラジドリシャーシの決定版!
【サーボ】
▶ ReveD RS-ST
(2025/10/08 16:49:45時点 楽天市場調べ-詳細)
→ ラジドリ用サーボの決定版ともいえるコスパモデルです!
【ジャイロ】
▶ ReveD Revox
→ ラジドリメーカーのReveDが手掛けるラジドリジャイロのスタンダードモデル
【ESC】
▶ ヨコモ BL-EP6
→ プログラムカード付きでコスパに優れ、扱いやすい初心者用ESC!